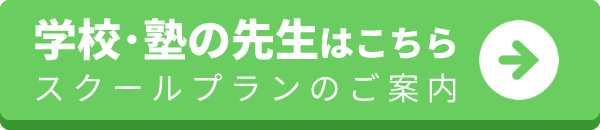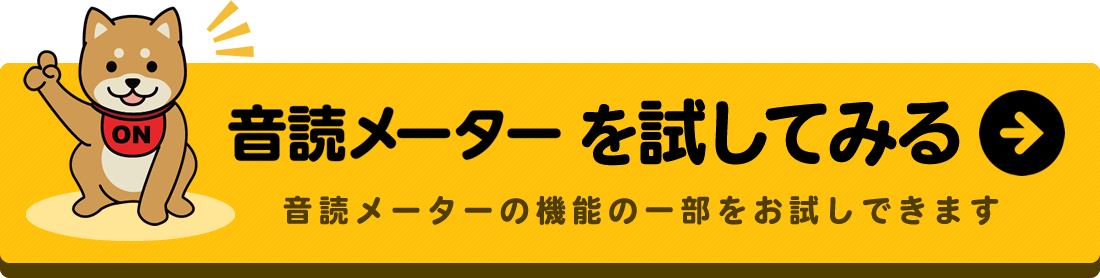ICT教育の先端を
走り続ける飯島先生
(関東学園大学附属高等学校)
が語る
音読メーターの魅力

関東学園大学附属高等学校
飯島先生
Points!
・音読メーターとの出会いと直感的な導入
・生徒の成長を「見える化」する学びの仕組み
ICTとの出会い ― 「給料数か月分のパソコンから始まった挑戦」
 ICTとの最初の出会いは、まだ世の中にパソコンが出始めたころでした。
ICTとの最初の出会いは、まだ世の中にパソコンが出始めたころでした。
そう語るのは、長年にわたりICTを活用した英語教育の実践を続ける飯島先生だ。
1995年頃、給料数か月分である50万円もするパソコンを購入。2000年ごろからエクセルのVBAマクロを独学で学び、英語の文法問題やゲーム教材を自作していたという。その革新的な取り組みはビジネス誌『日経IT21』の編集部の目に留まり、2002年に特集記事として紹介された。

音読メーターとの出会い ― 「これはすごい」と直感
そんなICT教育の先駆者が「音読メーター」に出会ったのは、東京で開かれた教育展示会だった。
 展示会で見たときは本当にびっくりしました。開発者の武藤先生のことは、以前から春や夏のセミナーで知っていて、“すごい人がいるな”という印象を持っていました。ある日、ICT関連のブログで音読メーターの記事を見つけて、すぐに資料を請求したんです。
展示会で見たときは本当にびっくりしました。開発者の武藤先生のことは、以前から春や夏のセミナーで知っていて、“すごい人がいるな”という印象を持っていました。ある日、ICT関連のブログで音読メーターの記事を見つけて、すぐに資料を請求したんです。
導入を決めたのは、直感的に“これは現場で使える”と感じたからだという。
授業での活用 ― 「まずは少しずつ、%を上げていこう」
飯島先生の授業では、主に教科書本文を中心に音読メーターを活用している。
 英語はやはり音声指導が大切です。最初は正答率が低くてもいいから、毎回少しずつ上げていこうと生徒に伝えています。達成条件はおおむね50%くらいに設定しています。
英語はやはり音声指導が大切です。最初は正答率が低くてもいいから、毎回少しずつ上げていこうと生徒に伝えています。達成条件はおおむね50%くらいに設定しています。
また、生徒によっては課題以外にも事務局から配信される“毎日英文”や、自分で練習したい英文を取り込んで自主的に音読する姿も見られるという。
教科書以外にも、単語練習や文法の例文を使うこともあり、音読活動の幅が大きく広がっている。
生徒の変化 ― 「隣のクラスに迷惑をかけないか心配なほど声を出すように」
音読メーター導入後、教室の雰囲気は一変した。
 生徒が驚くほど積極的に音読するようになりました。中には、あまりにも大きな声を出すので“隣のクラスに迷惑をかけないか”と心配になるほどです。
生徒が驚くほど積極的に音読するようになりました。中には、あまりにも大きな声を出すので“隣のクラスに迷惑をかけないか”と心配になるほどです。
特に、以前は音読活動をしていても本当に声を出しているのか分からないことがあったが、音読メーター導入後は“確実に発声している”ことがデータで確認できるようになったという。
指導のポイント ― 「高いスコアの鍵は、スピードと強弱」
 高い%を出すためには、ただ速く読むだけではだめです。適切なスピードと強弱が大切だと伝えています。
高い%を出すためには、ただ速く読むだけではだめです。適切なスピードと強弱が大切だと伝えています。
音声のリズムやイントネーションにも意識が向くようになり、生徒たちは“聞かせる音読”を意識して練習するようになった。
まとめ ― ICTを人の成長につなげる教育
2000年代初頭からICTを教育に取り入れ、今も現場で生徒と向き合いながら新しいツールを使いこなす飯島先生。
その原点には常に「生徒の学びを支える仕組みをつくりたい」という思いがある。
 道具は目的ではなく、手段。大切なのは、生徒が自分の成長を実感できることです。音読メーターは、そのサポートをしてくれる素晴らしいツールだと思います。
道具は目的ではなく、手段。大切なのは、生徒が自分の成長を実感できることです。音読メーターは、そのサポートをしてくれる素晴らしいツールだと思います。
そして最後にこう付け加えた。
 私の授業では、生徒は最初から最後までずっとiPadを使っています。ICTは“使うこと”が目的ではなく、“学びを広げるための当たり前の道具”になっています。
私の授業では、生徒は最初から最後までずっとiPadを使っています。ICTは“使うこと”が目的ではなく、“学びを広げるための当たり前の道具”になっています。